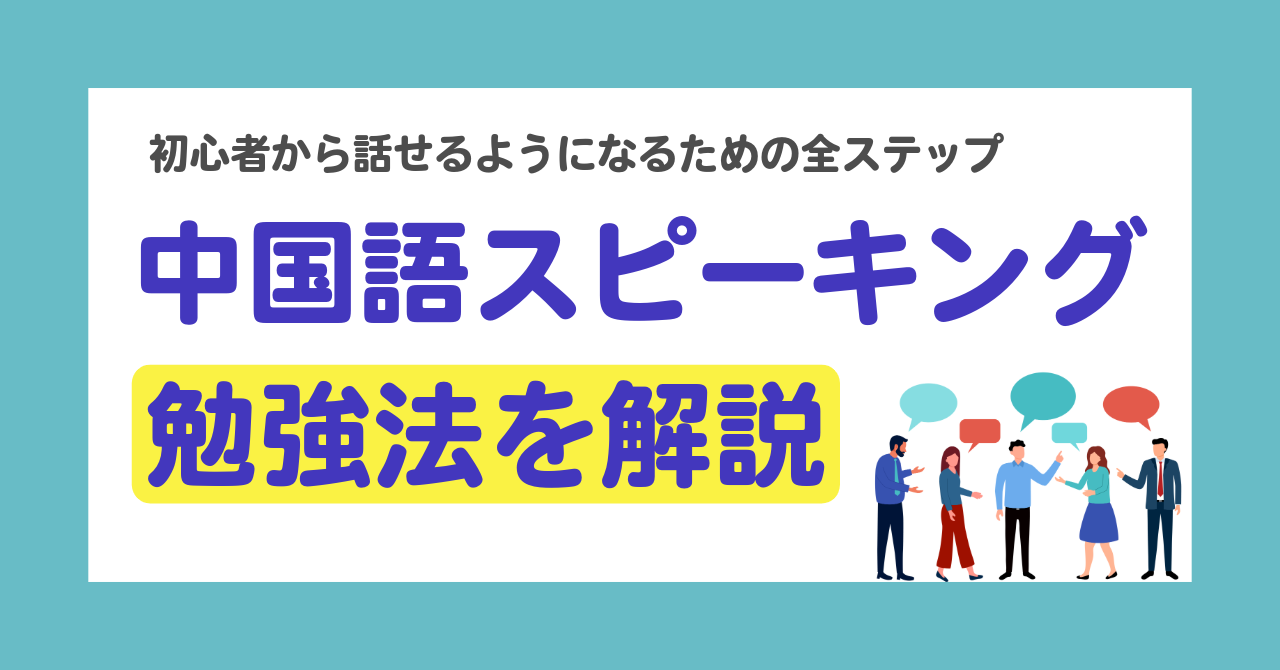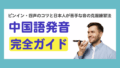「発音は一通り学んだけど、会話になると口が動かない…」
「中国語を読んだり書いたりはできても、“話す”のが一番苦手」
そんな悩みを抱える中国語学習者は、初心者だけでなく中級者にも非常に多くいます。
単語や文法の知識が増えても、“話す力”は自然には身につかないのが現実です。
では、どうすれば「言いたいことが口から出てくる」状態に近づけるのでしょうか?
本記事では、中国語スピーキングの勉強法を体系的に整理し、誰でも“話せる自分”に近づくための5ステップと練習法を紹介します。
独学でもOK。教材・アプリ・トレーニングの活用法まで、今日から実践できる内容を詰め込みました。
「学ぶ」から「使う」へ。今こそ、中国語を“話す力”へ変えていきましょう。
中国語が話せるようにならない3つの落とし穴
中国語の学習を続けているのに、なかなか話せるようにならない──
そんな悩みには、共通する原因=“落とし穴”があります。
ここでは、特に初心者〜中級者が陥りがちな3つのパターンを紹介します。
落とし穴①:インプットだけでアウトプットしていない
文法書を読んだり、単語を覚えたり、リスニングを頑張ったり──
学習の多くが「インプット」に偏っていると、「使う力」がまったく育ちません。
✅ ありがちな状態
- 単語の意味はわかるのに、会話になると一言も出てこない
- 知っている文法なのに、自分の言葉にできない
話せるようになるには、「実際に口に出す練習」が不可欠です。
アウトプットの量が少ないと、いくら知識を詰め込んでも会話力は上がりません。
落とし穴②:発音・声調を“自分の音”として定着させていない
中国語は発音が非常に繊細な言語です。
特に声調(トーン)や子音・母音の微妙な違いは、「通じるかどうか」に直結します。
✅ ありがちな状態
- ピンインは覚えているけど、声調はなんとなく
- 発音練習を「聞く」だけで終えてしまっている
つまり、「正しく発音しているつもり」でも、実際には通じない発音になっている可能性が高いのです。
“聞いて終わり”ではなく、自分の口から出した音を確認することがスピーキング上達の鍵です。
落とし穴③:「間違えるのが怖くて話さない」メンタルブロック
日本人学習者に非常に多いのが、「完璧に話せないなら、話さないほうがマシ」という思考です。
これは、学習効率を大きく下げてしまうブレーキになります。
✅ よくあるケース
- 頭の中で文を組み立てている間に会話が終わる
- 間違ったら恥ずかしいと思って、発話のチャンスを逃してしまう
言語は「伝わればOK」から始めるのが鉄則です。
“間違えてもいいから話す”という姿勢が、スピーキング力を最も早く伸ばします。
中国語が話せるようにならない原因は、才能やセンスではありません。
- インプット偏重でアウトプット不足
- 発音を「自分の音」として鍛えていない
- 間違いを恐れて発話を避けている
これらの「落とし穴」を回避し、正しいステップで進めることが、“話せる自分”への最短ルートです。
中国語スピーキング力を伸ばす5ステップ
中国語を話せるようになるためには、「発音を覚える」→「単語を並べる」では不十分です。
重要なのは、“口から自然に出る”状態を作るための順番=ステップ設計です。
ここでは、初心者〜中級者が確実に「言える・伝えられる」ようになるための5ステップを紹介します。
ステップ①:発音(ピンイン・声調)を自分の口で再現できるようにする
まずは、聞いた音をそのまま“自分の音”として再現できるかどうかが基本です。
✅ 実践方法:
- ピンイン+声調を「聞いてマネする」ではなく、「録音→聞き返し→修正」を徹底
- 破裂音・破擦音・鼻音など、日本語にない音を1つずつ集中練習
- 同じ声調・違う声調を組み合わせた単語を繰り返し練習
→ 「通じる発音」が身についていないと、どんなに話しても相手に伝わりません。
ステップ②:使えるフレーズを“丸ごと”覚えて口に出せるようにする
単語を並べるよりも、意味のあるフレーズを音で記憶する方が、実践会話では圧倒的に使いやすいです。
✅ 例:
- 你最近忙不忙?(最近忙しい?)
- 这个多少钱?(これはいくらですか?)
- 我还在学习当中(まだ勉強中です)
✅ コツ:
- 書かずに、聞いてマネして、繰り返し口に出す
- フレーズごと録音して、イントネーションやスピードもコピー
→ 「単語+文法」よりも、「状況+フレーズ」で覚えた方が、自然に口から出やすくなります。
ステップ③:スクリプト音読+シャドーイングで“口慣らし”する
ある程度発音とフレーズが口に馴染んできたら、実際の会話文を使って“声に出す練習”を行います。
✅ やること:
- 教材やアプリにあるスクリプト音声を聞きながら音読
- 慣れてきたら、スクリプトなしで音に合わせて復唱(シャドーイング)
- 自分の発音を録音し、ネイティブと比較して修正
→ これは単なる発音練習ではなく、「聞く力と話す力を同時に伸ばす」最も効率的なトレーニングです。
ステップ④:身近なことを中国語で“即興アウトプット”してみる
「書かれた中国語」を読むだけでなく、自分の生活に関係する内容を、自分の言葉で話す練習が必要です。
✅ 例:
- 今日の天気について1分話す(例:今天有点儿冷)
- 昨日何を食べたかを説明する(例:我吃了面条)
- 仕事で何をしたかを簡単に報告する
→ 自分の中にある言葉を中国語に置き換えていく作業が、“使える中国語”を育てます。
ステップ⑤:他人と話して「実戦の壁」を越える
最後は、「誰かと実際に中国語で話す」=アウトプットの本番です。
✅ 方法:
- 中国語教室や言語交換アプリでの会話練習
- CCレッスン(オンライン中国語会話)や天天中文などで週1回でも実践
- LINEやチャットアプリで簡単な文章のやりとりから始める
→ 完璧な文でなくてもOK。“話すことに慣れる”ことが上達の最大加速ポイントになります。
- 中国語は「順番」に沿って話す練習を進めれば、必ず成果が出る
- 発音 → フレーズ → 音読 → 自分語り → 実戦、という5ステップが基本
- いきなり“自然な会話”を目指すより、「まず口を動かすこと」が先
発音・語順・単語力を“話す力”に変えるトレーニング法
単語を覚えた、文法もわかってきた──
それでも「話せない」と感じるのは、それらの知識が“会話用のスキル”として変換されていないからです。
ここでは、発音・語順・語彙力を実際の発話に結びつけるトレーニング方法を具体的に紹介します。
トレーニング①:録音して「自分の発音を客観視」する
発音練習で最も効果があるのは、自分の声を録音して聞き返すことです。
✅ 手順:
- 短いフレーズ(例:我会说一点儿中文)を自分で発音
- 録音して、ネイティブ音声と聞き比べる
- 声調やリズム、音の抜け・強弱を確認して再チャレンジ
→ 「自分では正しく発音しているつもり」でも、聞くと驚くほどズレていることが多いのが中国語です。
この練習を続けることで、通じる発音が身についていきます。
トレーニング②:語順テンプレートを“音で覚える”
中国語は語順が命です。
でも、語順を毎回考えていては口が動きません。
そこでおすすめなのが、「語順テンプレート」を音で覚えること。
✅ 例:
- 主語+時間+場所+動作:我昨天在公司工作。
- 主語+要+目的語:我想学中文。
- 疑問文:你几点下班?你吃了吗?
→ こうした「型」をフレーズとして口に馴染ませておくことで、瞬時に話せるようになります。
トレーニング③:単語は“使う場面”とセットで覚える
単語を「日本語訳」だけで覚えても、実際に会話で使えることはほとんどありません。
重要なのは、“使い方込み”で覚えることです。
✅ 悪い例:「去」=行く、とだけ覚える
✅ 良い例:「我去超市买东西。」「明天你要不要一起去?」など使い方を覚える
→ 文脈とセットで覚えることで、口から自然に出てくる単語になります。
トレーニング④:日本語→中国語に即変換する“瞬間作文”
「聞いたことある」や「書いたことある」はあっても、“言えるかどうか”はまったく別の問題です。
そこでおすすめなのが、“瞬間作文”です。
✅ やり方:
- 日本語の短文を見て、それをすぐに中国語で言ってみる
- 例:
「今日は寒い」→ 今天很冷。
「ちょっと疲れた」→ 我有点儿累。
→ 頭の中にある情報を即座に中国語で表現する訓練は、会話力アップに直結します。
- 発音は「録音+比較」で自己修正が加速する
- 語順は“型で覚える”ことで会話に強くなる
- 単語は「使い方ごと覚える」ことで口に出しやすくなる
- 瞬間作文は“反射的に話す”力を育てる
おすすめ教材・アプリ・会話練習法|独学でもできる
「中国語を話せるようになりたいけど、教室に通う時間も予算もない」──
そんな方のために、独学でもスピーキング力を鍛えられる教材・アプリ・練習法を厳選して紹介します。
初心者〜中級者まで使えるものを中心に、効果と継続性を重視しました。
スピーキングに効く教材(書籍)
| 教材名 | 特徴 |
| 『耳が喜ぶ中国語』シリーズ | 音声付き。日常会話ベースでシャドーイングに最適。初級〜中級向け |
| 『《改訂新版》瞬訳中国語 初級編』 | 会話でよく使う表現を場面別に紹介。例文が豊富で即戦力になる |
| 『改訂新版 口を鍛える中国語作文―語順習得メソッド―【初級編】』 | 実践的なフレーズが丸ごと暗記できる。旅行・仕事にも対応可能 |
→ 書籍は「音声付き」「口に出しやすい構成」のものがベストです。
スピーキング特化アプリ
| アプリ名 | 特徴 |
| HelloChinese | 発音チェック+フレーズ練習。ゲーム感覚で続けやすい。AI添削も◎ |
| HelloTalk | ネイティブとチャット&音声で会話練習ができる。無料利用も可 |
| Super Chinese | AIが搭載された中国語学習アプリ。発音チェック、会話練習、リスニングなどゲーム感覚で学べる |
→ アプリは「録音してフィードバックがあるもの」「実際にやり取りできるもの」が特に効果的です。
会話力アップの実践法(オンライン活用)
CCレッスン(オンライン中国語会話)
- 月数千円〜でネイティブ講師と1対1の会話練習が可能
- スマホやPCで受講でき、時間の融通が利く
- 教材持ち込み可&自由トークも可能なので、自分の弱点強化に◎
→ 「会話相手がいない」「自分の話す力をチェックしてほしい」という方に特におすすめ。
スマホでできる簡単スピーキングルーチン(例)
| タイミング | 内容 | 所要時間 |
| 朝の通勤中 | HelloChineseで1フレーズ練習+シャドーイング | 約5分 |
| 昼休み | Super Chineseで音声チャット1通送信 | 約5分 |
| 夜 | 好きなフレーズを録音して聞き返す(耳と口の修正) | 約5〜10分 |
→ このように、「聞く+話す+チェック」の循環を毎日小さく回すことで、自然にスピーキング力がついていきます。
- 独学でも“話すための訓練”は十分できる
- 書籍・アプリ・オンライン会話を組み合わせて、弱点別に対策
- 大事なのは、「話す機会をつくる」意識と継続しやすい仕組み
「話す習慣」を無理なく続けるコツ
スピーキング力を伸ばす最大のカギは、“とにかく続けること”にあります。
しかし実際には、ほとんどの学習者が「忙しくて続かない」「話す機会がない」と感じてしまいがちです。
ここでは、中国語を話す習慣を無理なく継続するための工夫を5つ紹介します。
コツ①:1日1アウトプットを“ルール化”する
「やる気が出たときだけやる」では続きません。
大事なのは、“毎日必ず1回は話す”という仕組みをつくることです。
✅ 例:
- 朝起きたら1フレーズ口に出す(例:今天星期几?)
- 通勤中に1文だけシャドーイング
- 就寝前に「今日の一言」を録音する(例:今天我有点儿累)
→ “義務感”より“習慣”にしてしまえば、学習コストは大幅に下がります。
コツ②:「失敗してOK」というマインドセットを持つ
中国語学習者が話すことを躊躇する最大の理由は、「間違えるのが怖い」です。
しかし、言語は“試行錯誤の積み重ね”でしか上達しません。
✅ 自分にこう言い聞かせよう:
- 通じれば100点!
- 間違いは成長の証
- 正しい中国語より“伝わる中国語”が先
→ 完璧主義を捨て、“言ってみる”を最優先にすることが、スピーキング力を劇的に伸ばします。
コツ③:記録と可視化で「やった実感」をつくる
学習の継続には、「やってる感」=達成感が重要です。
そのために、学習記録を目に見える形で残すことを習慣にしましょう。
✅ 例:
- カレンダーに○をつける
- LINEの自分宛てにその日話したフレーズをメモ
- 録音を1日1本、ファイル名に日付をつけて保存
→ 目に見える記録はモチベーション維持に直結します。
コツ④:会話する相手や場面を“事前に決めておく”
人と話すチャンスは待っているだけでは来ません。
「誰と、いつ、何について話すか」を自分で決めておくことが大切です。
✅ 例:
- 毎週火曜夜にCCレッスンでフリートーク
- 土曜日にHelloTalkで中国人と音声チャット
- 日曜日は録音してYouTubeで“1人中国語日記”を投稿
→ 「予定に組み込む」ことで、練習は“非日常”から“日常”へと変わります。
コツ⑤:「話すこと自体を楽しめる工夫」を入れる
義務感だけでは継続できません。
楽しいと感じる瞬間を、学習の中に必ず混ぜてください。
✅ 楽しむための工夫:
- 自分の好きなジャンル(ドラマ、旅行、料理など)で話す練習
- 推しキャラになりきって1人寸劇
- “中国語だけの日”をつくる(例:日曜は独り言も全部中国語)
→ モチベーションではなく、“喜び”があるから人は続けられます。
- 毎日1アウトプットを“仕組み”にする
- 完璧を求めず、まず“伝える”ことに集中
- 記録・予定・遊びの要素で、学習を「苦行」ではなく「習慣」に
まとめ|話せるようになる人は、「続けられる仕組み」を持っている
「中国語を話せるようになりたい」──その願いを叶えるには、特別な才能や完璧な文法知識は必要ありません。
必要なのは、「順番」と「仕組み」です。
記事の要点を振り返ると:
| セクション | ポイント |
| 話せない原因 | アウトプット不足・発音が定着していない・完璧主義の壁 |
| 伸ばすステップ | 発音→フレーズ→音読→即興→実戦の5ステップで話す力が育つ |
| 効果的な教材 | 音声付き書籍・アプリ・CCレッスンなど独学対応のツール多数 |
| 続ける工夫 | 毎日の1アウトプット・記録・楽しさ・事前の場面設計などがカギ |
スピーキング力は「積み上げた量」と「話した数」で決まる
- 1日10分でも、正しい順番で口を動かす
- 完璧じゃなくていい、“言ってみる”ことが一番の練習
- 継続できる設計をつくれば、誰でも「話せるようになる」
あなたの中国語が「読む・聞く」だけでなく、「伝える・会話する」力に変わっていくよう、
このガイドがその一歩になれば幸いです。